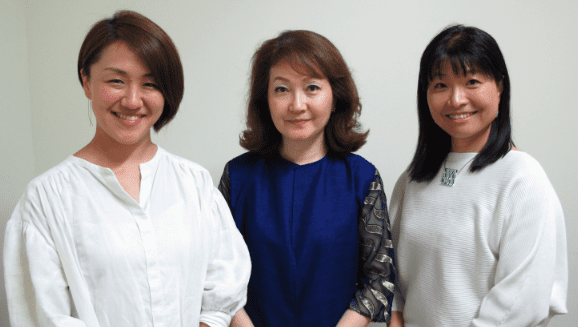
今回の座談会は、シンガポールで起業して10周年を迎えた女性起業家に集まっていただき、これまでシンガポールの変遷と共に歩んだ道のりについて熱く語ってもらいました。嬉しかったこと、辛かったこと、全ての経験が糧になり、今の彼女たちの人生をキラキラと彩っています。「私にしかできないこと」、彼女たちの「オリジナリティ」をもってどうやって邁進してきたのでしょうか。
目次
座談会参加メンバー
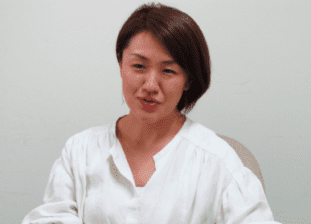
齋藤 真帆さん
CEO。神奈川県横浜市出身。2001年出版局へ入社し、大手メーカーへ転職した後、2006年シンガポールへ移住。 2009年シンガポールにVivid Creations Pte Ltd.を設立。イベント運営や展示会出展支援を中心に、日系企業や行政機関の海外プロモーションおよび、日系サービス・コンテンツの海外ビジネス開発およびマーケティング支援を展開。2014年 日本に株式会社Vivid Creations Japanを設立。2014-2016年「シンガポール和僑会」会長に就任。2016年には (一社)東京ニュービジネス協議会「国際アントレプレナー賞」特別賞受賞。 現在は複数の他団体と連携する共同プロジェクトを実施。様々な境目を越えた、新たな価値創造に取り組む。

Sachiyo(中垣 幸世)さん
シンガーソングライター・音楽プロデューサー・シンガポールセミナー講師。1972年シンガポール移住。シンガポール航空初の日本人キャンペーンモデル。1997年プロ歌手デビュー。4ヵ国語(日・英・中・マレー)で歌い創り、3枚のアルバムをリリース。2009年と2012年、天皇誕生日記念式典において、日星両国国歌独唱。2010年、NDP独立記念式典、COMPASS AWARDSに初の日本人シンガーとしてゲスト出演。日星音楽親善大使として多くの日星文化交流イベントに出演し、プロデュースも手掛ける。日星のバイカルチュラル・アイデンティティーを持ち、独自のシ
ンガポールセミナープログラムを構築、講演も多数。

酒井 奈美子さん
和太鼓奏者、響屋代表。2000年シンガポール移住。2007年に家族ユニット「天鼓」、2009年に「響屋」を設立し、太鼓スクールをスタート。当初は和太鼓中心だったが、現在では篠笛・三味線・日本各地のお囃子、民謡や芸能にも取り組
み、シンガポールに限らずロシアやカタール、インドなどでも公演実績を重ねる。2015年のシンガポール建国50周年(SG50)や、2016年の日・シンガポール外交関係樹立50周年(SJ50)の各種イベントでも演奏。アーティストや芸能グループをシンガポールに招致する活動も積極的に行っており、岩崎鬼剣舞(岩手県)、石見神楽(島根県)など様々なグループを呼び、実際に祭に参加するなど、交流を続けている。
シンガポールでの起業を選んだ理由
齋藤:2006年に現採(現地採用)で初めて来ました。25歳ぐらいの時から、とにかく海外で働きたいと思っていた。実家は横浜で、毎日東京まで通っていたんです。朝の東海道線は尋常じゃない混みようでした。都会に住むということはこういうこと、これが普通なんだとずっと自分に言い聞かせてて。周りのサラリーマンやOL、学生さんとかを見ても、ひたすら「無」になって電車に乗っている。最初はこれが普通で、みんなこうやって頑張ってんだと思うようにしていたのですが、だんだん、これでいいのかと違和感を持つようになって。次第に、これは多分、不自然なことなんだ、違う環境を選ぶ選択肢ももあるんじゃないか、という聞こえない声が聞こえてくるようになりました。
中垣:数ある外国の中で、なぜシンガポールを?
齋藤:NYやロンドンなどの欧米諸国も考えたんですけど、特段海外経験がない女子が果たしてやっていけるのか、あとビザを取るのに1年以上かかるかもしれないと言われて。好きな東南アジアで、かつ英語圏の国で探してたら、シンガポールがヒットしたんです。給与水準も日本とほとんど変わらないというところもポイントでした。タイも好きなので考えたんですが、その当時の現地採用の給与額では日々の暮らしは困らないだろうけど、何かあった時にすぐには日本に帰れないな、と思いました。それで、面接でそれまで来たことのなかったシンガポールに1週間滞在した時に、ここならすぐ住めるな、と思いました。世界各国の食事が食べられて、治安も悪くなく、人に関しても多国籍で、ここなら暮らしやすいだろうと。
酒井:私は2000年に来ました。親に「2年行ってきま~す」って言って出てきて20年目。
齋藤:長い!
酒井:当初は語学教師でしたが、日本の和太鼓を広げたい思いだけでここまできてます。
中垣:自分にしか出来ない事、オリジナリティって大事。私は1972年に家族でシンガポールに来まして、小中とシンガポールで過ごして、高校から日本。2009年初のパフォーマンスが国歌独唱で、君が代とシンガポールの国歌と両方歌ったんですが、私のオリジナリティという意味で、これで気持ちが固まった。バイカルチュラルである事をすごく大事にしていて、ハーフじゃなくて、ダブル。両方が分かっている、両国をつなぐ仕事をしたいと。
そもそもシンガポールで起業したきっかけは?
酒井:教師をやる一方で、大好きな太鼓をやりたいとくすぶっていた。でもあるのは、腕とばちだけ。和太鼓のイベントのパフォーマンスの話が来た時も、肝心の太鼓がない。その時主人に、これが太鼓買うきっかけになればいいと話をして。でなければ、夢見るだけで終わってた。あれは大変な転換期だったと思う。始めたら、あれよあれよと、人が集まってきて…。
中垣:やむを得ない事情で、どう選択するのかが、肝かもしれないね。
酒井:存続させることが使命。あの場所がなくなったら、あの熱い人たちはどこに行けばいいんだという使命感を常に持ってる。
オリジナリティを追求する
中垣:2008年の12月に元ル・クプルの藤田恵美さんのソロ・コンサートのオープニングアクトのお話を頂きまして。え、藤田恵美さん、エスプラナードコンサートホールですか?是非やらせて頂きたいと思った。でも、誰も私を知らないし、私がゲストで出る事も知らない。出番が来て、ステージにトコトコトコと出ていって、いきなり冒頭で2曲歌ったんです。1曲目は中国語で沖縄の歌「花」を、2曲目は自分のオリジナル曲をピアノの弾き語りで歌った。でも歌い終わったらね、割れんばかりの拍手を頂いたの。さざなみのような1600人のあの拍手を今でも忘れられないんです。あの瞬間、ここをベースにしたいと思った。育った国で勝負してみようと。
齋藤:2009年は今よりもたくさんの日系大手企業の拠点があったのに、大手広告代理店企業以外にイベントに特化した日系の会社がありませんでした。日本スタイルのイベントとか日本をテーマにしたイベント、日本から会社の上層部が参加するイベントなど、失敗が許されないプロジェクトの時に、日本語と英語でコミュニケーションがとれて、日本のクオリティでサービスを提供できる会社としてとして重宝していただきました。あの頃は、シンガポール島内で日系企業同士が頼りあっていた時代。隙間産業だったのでしょうね、今思うと。シンガポールも音楽やアートに関してもまだまだこれからという時。海外のいいモノを取り入れようという姿勢がオープンで。こんなに需要と供給が一致しているのに、なんでそれをつなげる人や企業がないんだろう、というのが始まりですね。
これまで苦労したこと、どうやってリカバーしたか、お聞かせください。
齋藤:失敗談ありすぎて…(笑)。中小企業の海外進出が加速したことで、日本国内のクライアント様からの売り上げが増えたので、日本支社を立ち上げたんです。シンガポールから日本に拠点を移したのですが、その時、出張感覚で、あとはちょっとよろしく!って感じで行っちゃったんです。そうしたら最終決定する人(私)が不在になることで、あっという間に組織が揺らいでしまいました。あくまでシンガポールが軸で、営業するための日本だったのに。なおかつその時期に妊娠をしたので、営業として社外での動きも鈍くなり、妊娠特有の精神的なアップダウンもあるし、いろんな面で当初の予定が思い通りにいかなくなりました。
どうやってモチベーションをあげたんですか。
齋藤:そんなすぐには上がらなかったです。自分なりに頑張っていたつもりだったのに、なかなかうまくいかない。根本的な問題は自分なのに。でも距離があったので、日常の自分の体から出るネガティブな雰囲気が直接伝わらずに済んだ。それが冷静に考えられる余裕になったのはよかったと思っています。これがオフィスで顔あわせて消極的で感情的な話をしてたらもっと悪くなっていたかもです。大事な局面ではいつもとことんスタッフと腹を割って話し合うようにしていました。
酒井:今話を聞いてものすごく大変だったと知ったけど、腹割って話せて、任せられる人がいるって、すごくいいと思う。
齋藤:私も最初は信頼する、任せたつもりでいて、心から信頼しきれてなかったのかもしれません。どんな失敗をしても私が責任とればいい、という度量と器が足りなかったんだと思います。今は拠点を日本に移して離れたり、出産があったり、任せざるを得ない状況になったのは本当にいいきっかけだったと思っています。信頼することで、みんなのやる気や能力がみるみる上がっていきました。
災い転じて福となす
中垣:レコーディング直前に声帯結節になって、ポリープの一歩手前のおできのようなものができて、歌えなくなったことがあったんです。医者は1ヵ月で治るかもしれないし、5年かかるかもしれないと言う。発声か何かが間違ってるんだと考えて、全部見直していったの。そうしたら1ヵ月で治って、以前より声が出るようになった。私の人生こういうことが多い。問題に対して一生懸命取り組むと、前よりもさらに良くなる。「SJ50コンサート(日・シンガポール外交関係樹立50周年記念)」の時は死ぬかもしれない、と何度も思ったくらい人生最大のイベントだったけれど。日本とシンガポールのトップアーティストに出演して頂いてのコラボレーションコンサート。
齋藤:すごい面々だったよね。
中垣:この最大イベントをプロデューサーとして全責任を負って一人でやるということに途中耐えられなくなってしまって。10万ドル単位の興行、自分一人で資金を集めて、スポンサーシップを取って。夜中1~2時くらいまでオフィスにいるということが1ヵ月続いていた。夜中にビジネスパートナーに電話して、あたしもうだめかもしれないとか言って泣きながら訴えたこともあった。でも辛い時、必ずだれか支えてくれる人がいた。ふとある時、これだけの大事業をやらせて頂いているんだから、もう死んでもいいや、と思った。私じゃないとできないと思い直して、自分を奮い立たせたの。結果、日本とシンガポールの音楽史上恐らく誰もやったことがないことをやれたと思う。
酒井:Sachiyoさんはすごいスケールの大きいことを、丁寧に着実にやるタイプ。お願いするときもしっかり資料用意して、終わった後にはお礼参りじゃなくて…。
一同:お礼参り!(笑)
中垣:お礼参りって…。「報告」の事ね。自分がやりたいことに資金を出して頂いたのだからご支援くださった方々にきちんと結果を報告することは大事と思う。収支報告ほか、全ての報告書を出して、ありがとうございましたとお礼を伝えたい。これは親に言われた事で、小さい時にその月の収支明細を出さないと次の月のお小遣いがもらえなかったのね。それが沁みついてる。
シンガポールのこれまでとこれから
この10年間、シンガポールの環境の変化など感じたことはありますか。
中垣:フェイスブックなどのSNSがこの10年すごく普及したと同時に、投稿やコメント内容、拡散される情報などに疑問を持つことが多くなった。それは正しい情報なのか、事実をきちんと確かめたのか。思慮深い日本人の良さが消えたような…。ネット上のリテラシーやマナーが非常に問われるようになった。そう言えば「ピンクドット(LGBTイベント)」が始まったのも10年前。この国で大々的にこのようなイベントが出来るようになったのはすごい。
齋藤:まず景観が変わった。ショッピングモールがさらに増えた。物価も変わって、10年前、日本なんて物価が高くて行けないって言ってたのが、年に何回も行くシンガポーリアンが増えましたね。
中垣:確かにGSSの時期は逆に日本に行った方が安いという話もある。今、シンガポールはなんでも高すぎる。コンサートの製作費も日本の倍かかります。
齋藤:ほんと、そう!でもチケット代は2倍じゃないから(ビジネスが)成り立たない。会場は日本の方が安いですよね。制作物も印刷代も。
酒井:安い安い。
中垣:日本に発注する方が安いとかそういう風潮になってくると、ちょっと残念ですね。文化に対してお金を払うという部分、もう少し育ってほしいよね。才能とかクリエイティビティということでは、オリンピックで金メダルが出たり、芸術面でもアカデミー賞を取った『ラ・ラ・ランド』のサウンドエンジニアがシンガポーリアンで、オスカーにノミネートされたりしてる。対日本でいうと、少し逆転した見方をされるようになったかも。
酒井:最近、海外で活躍するシンガポールアーティストも増えてる。やっぱり英語が喋れるのは強い。
中垣:アジアの大スター達のバックサポートを、シンガポーリアンがやっているんです。今、シンガポールのミュージシャンたちは台湾、香港、中国から引っ張りだこですよ。
酒井:レジデンスアーティストというのがいてね、(政府から)すごい手厚くサポートされてる。ずっと頑張ってた、大変なんだよって言ってた人たちがそういうのに選ばれると、おめでとうと思う反面、うらやましいなと思っちゃう。
中垣:そうだね。我々はその狭間に入っちゃうときがある。シンガポールの助成金はシンガポーリアンが優先。日本は、日本在住とか日本ベースの日本人アーティストが優先。その中で、どうやって自分のスペシャリティを訴えていくか。
齋藤:シンガポール永住権保持者(PR)だったらいいんじゃないの?コラボとか?
中垣:シンガポールのアーティストだけではなく、日本人アーティストも含めて日本とのフュージョンによって新しい文化価値を創出できると提案する。シンガポールの曲を日本の1400年の歴史を持つ楽器で奏でると違う世界観が生まれるとか。シンガポールの音楽文化に貢献できるという方法を提案し続けています。
酒井:ポテンシャルあるところにはお金、バン!と出しますよね。優秀な教授とか好待遇で引っ張ってきたり。アートに対しても、ポテンシャルのあるグループのサポートが、外部から見ても分かるような形でされていると思います。ホールもあるような新しい施設のスタジオとオフィスで活動しているような、できたばかりのアートグループもいます。10年前じゃそういう施設自体もそれほど多くなかったと思います。
シンガポールは今後どうなっていくと思いますか。
中垣:「異論を許容する多様性」が必要になっていくのでは。自由に表現できる、真の意味での多様性を許す多民族国家になってほしいという願いはあります。もちろん政府もそれに取り組もうとしているのは見えるのですが、まだまだ規制が多い。70年代は男性の長髪が禁止、ハードロック禁止。不良につながるからという理由で。ディック・リーさんはディープ・パープルが大好きだったのに、ポップミュージッシャンに転向せざるを得なかったようです。あと、雇用の問題などがあるのか、人へのサービスはもう少し頑張って欲しい。それを考えると、2029年ってどうなってるだろうね。
齋藤:なんでもオートメーション化されているかも。今の時点でも宅配BOXとかさまざまな手配や手続きがデジタル化されているのは日本より進んでいる。高齢化問題もあるから、AI化していかなきゃというのもあるんじゃないですか?
中垣:でもAIをコントロールするのは人間なんだよね。
齋藤:そこを言うと、読解力と効率的、合理的な部分での完遂能力はすごく高い人が多いシンガポールだけど、これからの教育で変わっていくのかなと思う。クリエイティブとかアートの推進とかに力入れてるでしょう。
中垣:PSLE(小学校6年生に受ける全国統一テスト)も段階的に廃止されるし、一芸入試で進学することも出来るようになってきた。
齋藤:セカンダリースクールでジャズコースもできるって聞いて、素晴らしいなと思って。ただ、これからは自分の専門分野に加えてプラスアルファ何かできる人が増えていきそう。コーワーキングスペースも最近増えてるし、活動は小さくても、いろんな人たちと共創しながらやっていく時代が来る。そこからイノベーションも生まれる。また創造力とか対話力などのコミュニケーション能力ってシンガポールのような多国籍社会ですごい大事だと思っています。柔軟性、順応力だよね。これがあれば、それだけでも可能性が無限に広がるし。
中垣:自分が主催者で、自らが運営していくアーティストが増えてきてる。アーティストがプロデューサーやマネージャーを雇ってね。ネットでの配信とかみてもシンガポール人は長けている。アーティストが「〇〇’s Room」とか自分のホームページで自分と他の業界の人と対談記事を載せていたりするの。
酒井:異業種どころか、もともと国内で、民族が違う人たちとやり取り慣れてるしね。
齋藤:外国人慣れしてるからね。
中垣:日本が本格的な外国人労働者の受け入れが始まった一方で、こちらは既に全体の4割近くが外国籍という…。
最後に一言お願いします。
齋藤:社会に必要とされること、自分にしかできないことをやっていれば続くと思っています。100年とか続くとかそういう意識はあまり考えていないです。社会のためになることを考えながらやっていたら続いてた、っていう自然な流れが望ましい。
酒井:「私だからできること、私にしかできないこと」をやっていくのが、私の道だと思っています。いただいた「ご縁」を大切に、目の前にあることを一つずつ丁寧に取り組んでいきたいです。
中垣:今、目の前にあることを一生懸命に向き合ってやっていけばいいんじゃないか、と。たくさん失敗した。でもそういうこと全部を経て、糧となって、今の自分となっている。今が一番いい。失敗も落ち込んだことも全部愛おしいもの。シンガポールで10年活動を継続できたのは、家族の理解と協力があってこそで、本当に感謝しています。